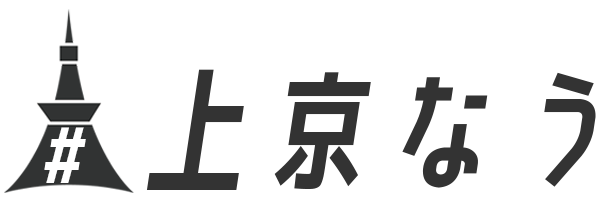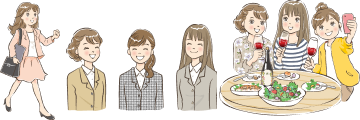就職と同時に上京してきました。
今は丸の内の不動産会社で営業マンをしている"マミ"です。
「初めての東京なのでうまく移動できるか心配」
「東京には路線も駅もたくさんあるので、乗り換えがうまくいくか心配」
地方から上京する場合、電車移動に不安を持っている人も多いですよね。
本記事では東京でスムーズに移動するために事前にしておくべきこと・注意すべきことを具体的に解説します。
東京に行く前に、ぜひ頭に入れておいてくださいね。
【7ステップ】東京でのスムーズな電車の乗り方

まず、7つの手順で東京でスムーズに電車に乗る方法を紹介します。
- SuicaかPASMOを購入する
- 乗り換えアプリを利用する
- 駅名だけでなく路線名を一緒にチェックする
- 電車の行き先と出発時刻をチェックする
- 乗り換えに便利な車両に乗る
- 正しい改札から出る
- 目的地の最寄りの出口から出る
SuicaかPASMOを購入する
東京で電車に乗る場合は、必ず交通系のICカードを買いましょう。代表的なものは「Suica」「PASMO」です。
- 乗り換えが多い場合、いちいち切符を買う手間が省ける
- 東京には会社をまたいで直通運転をしている電車が多いが、どこにいくら払うべきか計算する手間が省ける
- 手持ちの現金がなくても支払いできる
地方のカードを持っている場合はそれを使用しても問題ありません。
| 地域 | カード名 |
| 北海道 | Kitaca |
| 東日本 | Suica・PASMO |
| 東海 | manaca・TOICA |
| 西日本 | ICOCA・PiTaPa |
| 九州 | SUGOCA・はやかけん・nimoca |
ICカードは駅の券売機でも買えるので、手軽に入手できます。購入時にデポジットを支払いますが、カードが不要になった場合は駅でカードを返却すればデポジットも返金されます。
またカード型以外にも、スマホアプリで「モバイルSuica」をダウンロードすることも可能です。カードへの残高チャージをスマホで完結させたい場合はアプリの使用もおすすめです。
乗り換えアプリを利用する
東京で電車移動する場合は、乗り換えアプリが必須です。
なぜなら、最短で行くルート・最安値のルート・乗り換えが少ないルートと、ルート選びの基準はさまざまあるため。
例えば大手町から浅草に行く方法は3通りあります。
- 大手町(東京メトロ東西線)〜日本橋(東京メトロ銀座線)〜浅草
- 大手町(東京メトロ東西線)〜日本橋(都営浅草線)〜浅草
- 大手町(東京メトロ半蔵門線)〜三越前(東京メトロ銀座線)〜浅草
地図を見ながらルートを決めるのは難しいため、アプリで検索するほうが早いでしょう。
駅名だけでなく路線名を一緒にチェックする
東京では、駅名だけを見て改札に入ると、目当ての電車が見つからないこともあります。
というのも、同じ駅名なのに違う路線が走っていることも多いためです。
例えば「渋谷駅」といっても、9つの路線が入っています。
路線を確認せずに違う路線の改札に入った場合、「間違えて入ってしまった」と説明しても入場料を取られるケースがあります。
東京では、必ず「駅名・路線名」をセットで確認してから改札を通りましょう。
電車の行き先と出発時刻をチェックする
ホームに着いたあと注意すべきは、電車の行き先と出発時刻です。
地方では上り・下りの2方面への電車しかないこともありますが、東京の路線図はかなり複雑です。
自分が乗るべき電車の行き先・出発時刻を両方チェックしておかないと、余計なお金を取られたり時間をロスしたりする可能性があります。
- 同じホームなのに行き先が違う電車が来るから
- 同じ行き先でも経由地が違うケースがあるから
- 会社によって「特急」は有料・無料のケースがあるから
- 車両によって有料・無料のケースがあるから
- 時間によっては指定席がある会社・車両があるから
間違った電車に乗らないため、余計な料金を支払わないためにも、電車に乗る前に「行き先」「出発時刻」を両方チェックしておきましょう。
乗り換えに便利な車両に乗る
ホームで電車を待つ間に「どの辺りの車両に乗ればいいか」を確認しておきましょう。
乗換案内のアプリを使用すると、乗り換えに便利な車両は「前・中・後」のどのあたりかを教えてくれるものもあります。
駅によっては乗り換えのために10分以上歩くこともありますし、反対に乗り換え時間がとても短いことも。
地方より車両が多いので、乗る車両を誤ると乗り換えに必要以上に時間がかかり、次の電車に間に合わない可能性も。乗り換えに便利な車両に乗ることも重要です。
正しい改札から出る
電車を降りたら、目的地に辿り着くために正しい改札から出なければなりません。
- 乗り換え専用改札を通ってしまい、外に出られない
- 目的地から遠い改札から出てしまい、地下からの移動が難しい
- 間違えて隣り合う駅に辿り着いてしまう
人の流れに合わせて改札を通ってしまうと、上記のようにミスしてしまう可能性があります。
電車を降りたら、目的地に辿り着くにはどの改札から出るのがベストなのか確認しておきましょう。
目的地の最寄りの出口から出る
最後に、目的地に最速で辿り着くために、最寄りの出口から出る必要があることを覚えておいてください。
東京の駅は地下にあることも多く、出口によっては目的地から非常に遠い場所に出てしまうケースも。
出口が10箇所以上ある駅も珍しくないので、目的地の最寄りの出口はどこなのかをマップで確認し、その番号の出口を目指して歩いてくださいね。
東京で電車に乗るときの6つの注意事項

東京の電車は地方と違う点も多く、注意しておかないと自分が困ったり、周りに迷惑をかけてしまったりすることがあります。
トラブルにならないように、以下の6つの注意事項を理解しておきましょう。
- 想像以上に路線図が複雑なことを知る
- 電車の待ち列は数種類ある
- 体調が悪いときは満員電車に乗らない
- 満員電車ではカバンを体に密着させる
- 大きな駅での待ち合わせは具体的に場所を決める
- 「電車は遅延する」と思っておく
想像以上に路線図が複雑なことを知る
東京の路線図は想像以上に複雑です。
例えば、JRに乗っていたはずなのに降りるときには違う鉄道会社の駅に着いている、ということも多いでしょう。
相互乗り入れや直通が多いため、上記のようなケースが発生しやすいのです。
路線が複雑に絡み合う点は、地方とは大きく異なるため、「そういうこともある」と覚えておかなければ混乱してしまうかもしれません。
電車の待ち列は数種類ある
電車の本数が多い駅では、ホームに待ち列が描かれているケースがあります。
- 「先発」「次発」のような、順番を表示している
- 「〜方面」と行き先別になっている
以上のように、駅によって待ち列の種類が違うため、自分が乗りたい電車をきちんと調べて、正しい待ち列に並びましょう。
体調が悪いときは満員電車に乗らない
東京の満員電車は、地方のそれとレベルが違います。
あまりの混雑さに「本当に潰されそう」と感じることも多いため、体調が悪いときに乗るのはおすすめしません。
人の多さに酔ったり、酸素が薄く苦しくなったりしてしまい、体調不良がさらにひどくなる可能性があるためです。トイレがない電車では、トイレに駆け込むこともできません。
さらには、あまりにも人が多いと駅で降りるのも一苦労です。なかなか周りの人が避けてくれないとき、力ずくで道を開けなければならない、なんてことも日常茶飯事。
急ぐ必要がないのであれば、時間をずらして電車に乗ることをおすすめします。
満員電車ではカバンを体に密着させる
満員電車に乗る際は、カバンを体に密着させて乗りましょう。
路線によっては「リュックは体の前で持つように」と、アナウンスも流れます。
トートバッグなども、体から離していると人混みに紛れてどこかへ行ってしまうこともあります。しかし満員電車でカバンが手元から離れると、追いかけることはほぼ不可能。
カバンを無くしたり、最悪の場合中身を盗られたりするリスクをなくすためにも、カバンは必ず体に密着させてください。
大きな駅での待ち合わせは具体的に場所を決める
東京の大きな駅の規模は、地方の駅の規模と比べものになりません。
「新宿駅で集合」「渋谷駅で集合」とだけ取り決めていても、集合するのはまず不可能です。
1日に200万人以上の人が利用する駅も多いので、「新宿駅◯◯線の◯◯改札付近」のように、必ず具体的な場所を待ち合わせ場所として指定しましょう。
改札を出てから待ち合わせ場所に移動するのは難しいケースもあるので、先に場所を決めておくのがおすすめです。
「電車は遅延する」と思っておく
電車の数が多いため、東京では遅延も起こりやすいです。
「電車は遅延するもの」として行動することをおすすめします。
もしも絶対に遅れられない用事があるなら、早めの電車に乗るように計画を立てておきましょう。
ただし、東京では複数路線が走っているケースが多いので、迂回ルートを検索できます。
「遅延した場合にはどのルートで行けばいいのか」をあらかじめ検索し理解しておけば、焦ることなく移動できるでしょう。
まとめ
東京でスムーズに、間違いのないように電車に乗るためには、事前知識を入れておく必要があります。
さらに、電車にうまく乗れたとしても目的地まで辿り着くにはいくつもの関門が。
地方の電車のイメージで乗ってしまうと間違ってしまう可能性も高いので、本記事で紹介した7ステップの乗り方を参考にし、注意事項を頭に入れたうえで移動してくださいね。
東京での生活を始める人は、電車の乗り方に早急に慣れる必要があります。しかし毎朝駅の人混みがすごいため、辟易することもあるでしょう。
人混みとうまく付き合う方法も紹介しているので、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。