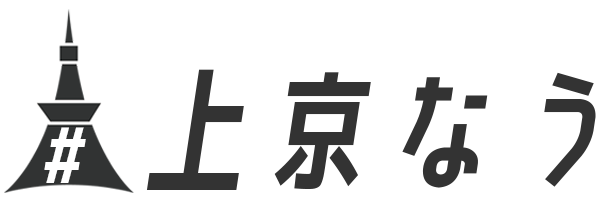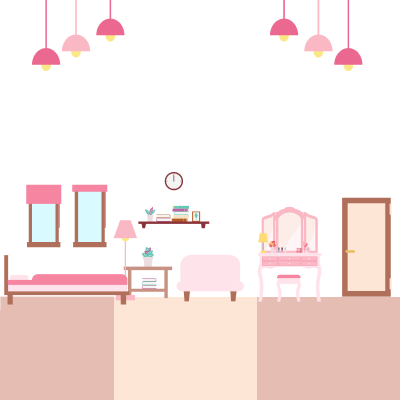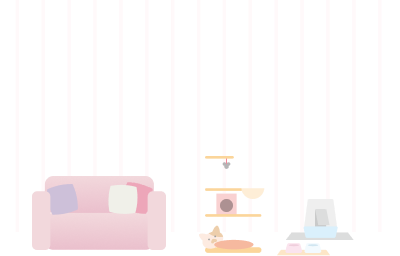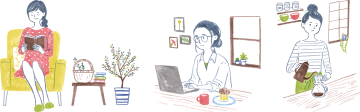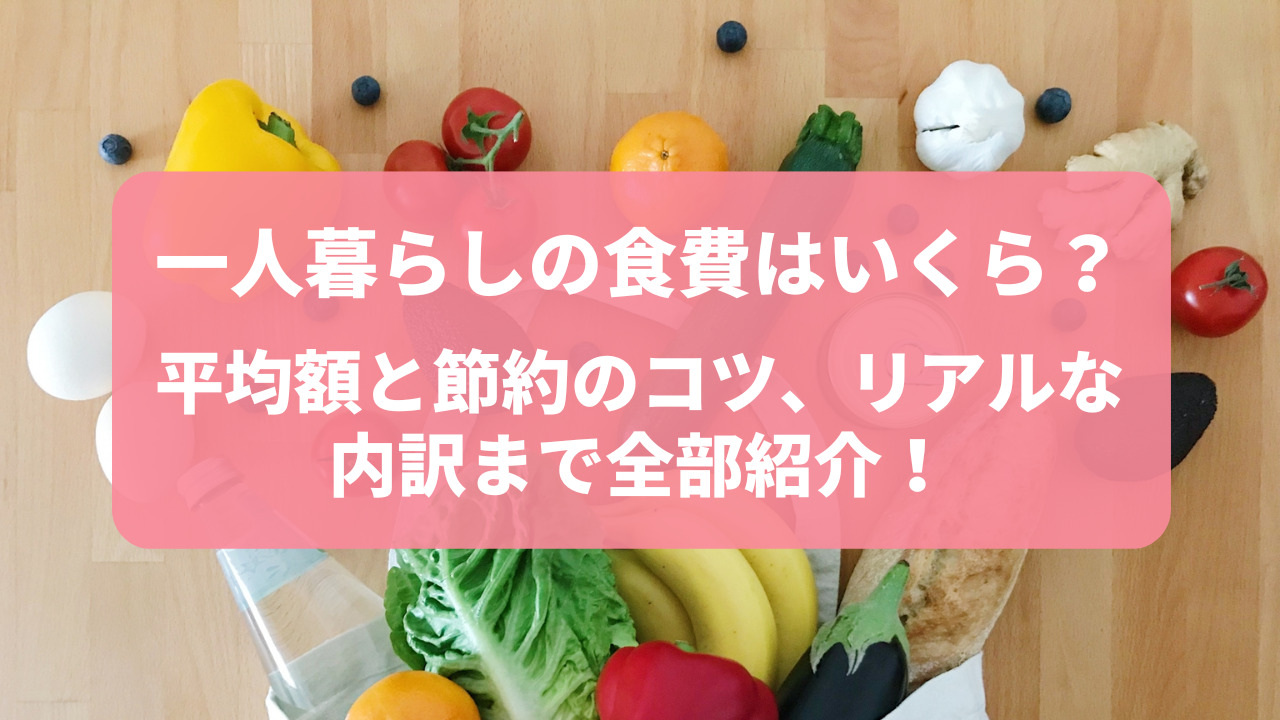

就職と同時に上京してきました。
今は丸の内の不動産会社で営業マンをしている"マミ"です。
一人暮らしを始めるとき、多くの人が気になるのが『毎月の食費』ではないでしょうか。スーパーでの買い物、コンビニでの小腹満たし、たまの外食…これらを全部合わせるといったいいくらかかるのでしょう。
SNSでは「食費は月1万円で十分!」という投稿を見かけることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか。「思ったより高い!」と驚く人も少なくありません。
この記事では、最新の調査データをもとに、一人暮らしの食費の平均額をご紹介します。
さらに年収やライフスタイル別の違い、実際の内訳、そして無理なく続けられる節約のコツまで、あなたの生活に役立つ情報をお届けします。
これから一人暮らしを始める方はもちろん、「もっと食費を見直したい」という方にもぜひ参考にしてください。
もくじ
一人暮らしの食費の平均はいくら?

一人暮らしの食費の平均額は、2023年の最新データによると月に約39,000円から42,000円の間となっています。これは総務省の家計調査や各種民間調査を総合した数字です。
特に会社勤めの勤労世帯では、平均で月に43,000円前後とやや高めの傾向が見られます。これは、平日のランチや仕事帰りの夕食など、外食の機会が増えることが主な理由です。
ただし、この平均額は外食の頻度や生活リズムによって大きく変わってきます。
自炊を中心にしている人と、ほぼ毎日外食やデリバリーを利用する人では、月に2万円以上の差が出ることも珍しくありません。
年収・性別・ライフスタイル別で食費はどう変わる?

一人暮らしの食費は、年収や性別、そして日々の生活スタイルによって大きく変わってきます。
それぞれの特徴を見ていくと、自分の食費の傾向や今後の見通しが立てやすくなるでしょう。
- 年収が高いほど食費も高くなる傾向あり
- 男性は女性よりも月8,000円程度高め
- 「節約タイプ」「外食タイプ」で大きく差が出る
年収が高いほど食費も高くなる傾向あり
年収と食費には明確な相関関係があります。各種調査によると、年収100万円未満の一人暮らしの方の食費は月に3.2万円台であるのに対し、年収600万円以上になると月に5.7万円を超えるケースが多くなっています。
これは収入に余裕が出てくると、「今日は疲れたから」と外食やデリバリーを選ぶ頻度が自然と増えるためです。また、食材もより高価なものを選びやすくなる傾向があります。
ただし、高収入だからといって必ずしも食費が高くなるわけではありません。年収が高くても計画的に食費をコントロールしている人も少なくありません。
大切なのは自分の収入に合わせた適切な食費設定をすることです。
男性は女性よりも月8,000円程度高め
性別による食費の違いも顕著です。特に若い男性(34歳以下)の食費は平均で約47,500円と、同年代の女性と比べて月に8,000円ほど高くなっています。
この差の主な理由は、男性の方が総じて食事量が多いことに加え、外食や飲み会などの付き合いで出費が増えるケースが多いためです。
また、自炊の頻度も関係しており、調査によると女性の方が自炊をする割合が高く、それによって食費を抑えている傾向があります。
とはいえ、これもあくまで平均値であり、個人の生活習慣や嗜好によって大きく変わってきます。自分の食生活を振り返りながら、適切な予算を考えるきっかけにしてください。
『節約タイプ』『外食タイプ』で大きく差が出る
食費は何よりも日々の食事スタイルによって大きな差が出ます。自炊中心の節約タイプであれば、月に20,000円から30,000円台に抑えることも十分可能です。
計画的な買い物と効率的な調理を心がければ、栄養バランスを保ちながらもコストを抑えられます。
一方、外食やコンビニ食が多めのタイプでは、月に50,000円を超えることも珍しくありません。
特に仕事が忙しい時期や、料理が苦手な人はこうしたスタイルになりやすいでしょう。
自分がどちらのタイプに近いかをまずはイメージしてみることが大切です。そして、今の食生活が自分の収入や健康面から見て適切かどうかを考えてみましょう。
必要に応じて少しずつ習慣を変えていくことで、理想的な食費に近づけていくことができます。
一人暮らしの食費の内訳と金額

一人暮らしの食費は何にどれくらい使っているのでしょうか。実際の内訳を知ることで、自分の食費の使い方を見直すきっかけになります。
- 外食・惣菜がダントツで高い
- お菓子・飲み物・お酒の”なんとなく出費”も意外と高い
- 基本の食材(野菜・肉・穀類)はバランス良く使って
外食・惣菜がダントツで高い
食費のなかで最も大きな割合を占めるのが外食と惣菜です。総務省の家計調査によると、一人暮らしの場合、外食には月に約7,800円から9,600円、調理済み食品には約7,500円台を使っています。
これらを合わせると月に1.5万円を超える支出になり、食費全体の3分の1以上を占めることになります。
「今日は疲れたから」「時間がないから」と惣菜やテイクアウトを買うことが積み重なると、かなりの出費になってしまうのです。
もちろん外食や惣菜を完全に排除する必要はありませんが、頻度や選ぶ店を少し意識するだけでも、月末の家計に大きな違いが出てきます。
お菓子・飲み物・お酒の”なんとなく出費”も意外と高い
ちょっとしたものの積み重ねも、実は大きな出費になります。調査によると、一人暮らしの方の菓子類への支出は月に約3,000円、飲料は約3,300円、酒類は約2,200円となっています。
これらのなんとなく買ってしまう出費を合計すると、月に1万円近くになることも。
コンビニでの衝動買いや、ちょっとしたご褒美としてのスイーツなど、気づかないうちに積み重なっている金額は意外と大きいものです。
こうした支出は完全になくす必要はありませんが、メリハリのある買い方を心がけることで、より満足度の高い使い方ができるようになります。
基本の食材(野菜・肉・穀類)はバランス良く使って
自炊の基本となる食材への支出は、野菜・海藻類が月に約3,600円、穀類が約2,600円、肉・魚などのたんぱく源が約4,500円となっています。
これらの基本食材は栄養バランスを考えると欠かせないものですが、上手に使えばコストパフォーマンスも高く、健康的な食生活を送ることができます。
特に穀類や豆類などは単価あたりの栄養価が高く、経済的にも優れた食材です。
バランスの良い献立を心がけることで、健康面でもお財布の面でもメリットが大きいといえるでしょう。週単位でメニューを考え、無駄なく食材を使い切る習慣をつけることが大切です。
一人暮らしの食費と収入の理想的なバランスは?

食費はいくらが適切なのか、その目安を知っておくと家計管理の助けになります。一般的には、手取り収入の10〜15%程度を食費に充てるのが理想的だといわれています。
つまり、月収20万円の場合は、2〜3万円が適切な食費の目安となります。
もちろん、これはあくまで目安であり、他の固定費(家賃や光熱費、通信費など)とのバランスを考えることが重要です。特に家賃が高い都心部では、食費の割合を少し抑えめにする必要があるかもしれません。
大切なのは、毎月の収支がマイナスにならないよう管理することです。食費だけでなく、固定費全体の見直しを定期的におこない、バランスの取れた家計を目指しましょう。
また、食事は日々の楽しみでもあります。食べたいものをすべて我慢しすぎないことも、長く続けるためのコツです。
週に一度の特別な外食や、好きなスイーツなど、自分へのご褒美を適度に取り入れながら、無理のない食費管理を心がけましょう。
食費を節約したいなら押さえたい4つのポイント

食費を節約したいと思っても、どこから手をつければいいか迷うものです。ここでは、無理なく継続できる食費節約のポイントを4つご紹介します。
- 自炊を習慣にしよう
- 買い物は作戦を立てておこなう
- 外食・コンビニは『週に〇回まで』ルールを決めて
- ふるさと納税でお米・お肉をゲット
自炊を習慣にしよう
食費節約の基本は何といっても自炊です。外食や惣菜に比べて、同じメニューを作るとコストが半分以下になることも珍しくありません。
自炊の強い味方となるのがもやし、豆腐、鶏むね肉などの定番節約食材です。これらは栄養価が高いわりに値段が安定しており、いろいろな料理に活用できます。
特にもやしは100円以下で大量に使え、炒め物や鍋、スープの具など万能に使える優れものです。
また、時間のある休日にまとめて調理する作り置きや、余った食材や料理を小分けにして冷凍保存する方法も効率的です。これにより平日の料理の手間を減らせるだけでなく、食材の無駄も減らせます。
料理初心者でも安心のレシピアプリも活用しましょう。食材から検索できるアプリなら、冷蔵庫にある材料ですぐに作れるメニューを提案してくれるものもあり便利です。
買い物は作戦を立てておこなう
節約上手な人は、買い物にも戦略があります。まず押さえたいのが特売日や閉店前の値引きを狙うこと。
多くのスーパーでは曜日ごとに特売品が変わったり、閉店1〜2時間前になると生鮮食品が大幅値引きされたりします。こうしたタイミングを把握しておくだけでも、大きな節約になります。
また、スーパーに行く前に買い物メモを作っておくことも重要です。メモなしで買い物をすると、必要以上の食材を買ってしまいがちです。
特に空腹時の買い物は衝動買いが増えるので注意しましょう。
さらに、まとめ買いは必ずしも節約にならないことも覚えておきましょう。特に生鮮食品は使い切れる量を買うことが大切です。
安いからといって大量に買って結局捨ててしまっては本末転倒です。自分の食生活に合った適切な量を見極めることが重要です。
外食・コンビニは『週に〇回まで』ルールを決めて
完全に外食やコンビニ食を避けるのは現実的ではありません。大切なのは、利用頻度にルールを設けることです。
例えば「外食は週に1回まで」「コンビニ弁当は疲れた日だけ」など、自分なりの基準を決めておくと継続しやすくなります。
このようにルールを設けることで、外食がいつもの習慣から特別なごほうびに変わり、満足度も上がります。また、計画的に外食を楽しむことで、前後の食事で調整するなど、バランスを取りやすくなるメリットもあります。
無理なくルールを守れるよう、自分の生活リズムや好みに合わせた基準を設定してみましょう。
ふるさと納税でお米・お肉をゲット
意外と見落としがちなのがふるさと納税の活用です。ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除される仕組みになっています。
つまり、実質2,000円の負担でさまざまな特産品がもらえるのです。
特に一人暮らしの方におすすめなのが、お米や肉類、冷凍食品などの返礼品です。
10kgのお米や、数kgの牛肉・豚肉などが選べる自治体も多く、主食や主菜を効率的に確保できます。特に精米済みのお米や使いやすく小分けされた冷凍食品は、料理初心者にも便利です。
年収や家族構成によって控除限度額は異なりますが、一般的な一人暮らしであれば年間数万円程度の寄付が可能です。これをうまく活用すれば、年間の食費を数千円から数万円節約することができるでしょう。
まとめ
一人暮らしの食費については、平均で月に約39,000円から42,000円であることがわかりました。ただし、この金額は年収や性別、そして何より生活スタイルによって大きく変わってきます。
理想的な食費の目安は手取り収入の10〜15%程度とされていますが、大切なのは自分の収入と支出のバランスを取ることです。無理な節約で食事を楽しめなくなっては続きません。
自炊を基本としながらも、時には外食を楽しみ、計画的な買い物で無駄を減らし、使い切れる量だけを購入するようにしましょう。
そうしながらも外食やコンビニ利用にはルールを設けてメリハリをつけたり、そしてふるさと納税などの制度も賢く活用したりすれば、健康的で満足度の高い食生活と、適切な食費のバランスを実現できるでしょう。
自分の生活スタイルに合った食費の使い方を見つけることが、充実した一人暮らしの第一歩です。
この記事が、あなたの食生活と家計管理の参考になれば幸いです。